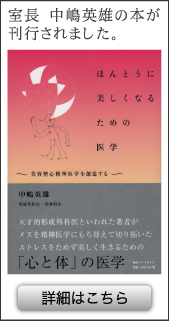*都知事になる為のパーソナリティ―「舛添気質」なるもの
舛添要一東京都知事の政治資金私的流用が問題になっている。
誰しも身の周りには、常に人の金にたかるのを信条とするような人は必ずいるものであり、決して特別珍しくもなく、ケチな下品な奴ですむが、政治家と言う人の上に立つ公人が公金を使うとなれば話は別になる。
週刊紙の記事によれば、知事のかつての友人のコメントとして、彼は東大の学生時代から、金持ちの娘としか付き合わず、常に彼女の親に援助を仰いで(たかって)いたという。これは証明のしようのない噂話ではあるのだが、妙に合点がいく話ではないか。
密をたたえた美しい花(美味しい餌)を常にさがしまわる性格が彼をして、政治学者より評論家、そして政治家へ、それも自民党歴代内閣の厚労大臣を経て、新党改革代表に転じたが、都知事になれるなら自民党にまた返り咲くという芸当を演じさせたのだろうか。彼の政治的信条の無さ、無節操さもすべて彼の嗅覚の招くところであったのだろう。厚労大臣時代の所作については既に書いた。(2015.8.12)
公用車の使い方にしても海外視察旅行の過剰経費にしても、規則に違反していない、法的にクリアされているから全く問題ないと言うが、公金と言う税金は使えるだけは使っていいと理解するところが基本的にずれているのだ。
自分の金でなければ、湯水のように使いまくって、それを問われると会計責任者の処理ミスのせいにして、開き直って居座ろうとする。何処かで見た景色だなあと思えば、徳洲会から5000万円を借りてとぼけていた猪瀬前都知事、前回の東京オリンピック誘致で数百億の不明朗な会計をし、開き直った石原前々都知事も同じように、公金を自分の金以上に好きなように使いまくった。
彼らは、たまたま権力を持ったから、つい魔が差したのだ、と言う人もいるが、僕はそうは思わない。これはパーソナリティの問題だと思う。
彼らに共通するパーソナリティは、常に利己を求めて渡り歩き、エサに喰らい付いたら、とことんむさぼり尽く人々、人のものならいくらでも使おうとするが、自分のものには極端にしまりが良く、そして不都合がばれると、とにかく言い訳をする、嘘と分かっていても屁理屈で突っ張り通す、そして自分の立場を守るためには、ときには強圧的に居丈高にどんな強弁、詭弁でも弄することが出来る人であり、つまり人としての基本的な品性の欠落した独特のパーソナリティのことを言う。
ここではそれを「マスゾエ気質」としよう。
彼等は都政にヴィジョンがあって都知事になったのではなく、権力が欲しくて、もっと言えば権力についてくる莫大な恩恵、利得が欲しくてなったとしか思えない、その後の振る舞いである。石原前々都知事は、オリンピック招致運動に絡め美術家の息子に莫大な顧問料を払ったうえ、最後は尖閣列島を都民の金で買うと言い出す公私混同ぶりであった。猪瀬前知事は、道路公団改革委員の時代に年間一千万近いタクシー代を使ったというし、副知事時代に覚えた手口で、石原氏以上に豪華な海外視察旅行を繰り返し、貧乏時代に借りた大金が、端金に思う様になったのか、しらばっくれていたら足をすくわれた。舛添氏は調子に乗って前任者二人よりほんの少し派手に使ったにすぎないのだが、家族やプライベートの美術品の分まで払わせ、センテンススプリング(週刊文春)の格好の標的になってしまった。ただ、報道は、公金の使用額の比較相手を猪瀬、石原両氏だけにしているから、並はずれて多くはないように見えるが、他都道府県の知事に比べると桁違いなのである。
最近になって東京オリンピックの誘致に、2億2千万円が、投票権を持ち、かつ大きな影響力を持つとされた国際陸連の会長に支払われていたことが明らかになったが、当時の下村文科相はその事実は寝耳に水であるというような弁明じみた発言をテレビ番組で言っていたが、その額は裏金でもなく、きちんと報告書にも記載があったから、大臣はその記載を見逃していたことになる。これは、いかに大きな金がメクラ判で大雑把に扱われていたかということを示すものであり、きっと他にもいろんなWOCのメンバーに支払われていたに違いあるまい。
あのIOCでの決定の瞬間の大喜びの映像は、今となっては白々しい。
実際のオリンピック事業では、千億単位の金が動くのだから、「マスゾエ気質」を持つ政治家、役人、スポーツ関係者、公共事業者は笑いが止まらない、殆ど濡れ手に粟状態になるに違いあるまい。もう既に、招致費用、競技場建設費用、エンブレム選考問題でも、その馬脚は現れているが、これから一体どれだけの公金が闇から闇に消えていくか想像することさえ出来ない。
今後、舛添氏が知事に居座れるかどうかは微妙だが、猪瀬氏の徹(辞めてしまえば、ただの人)は踏まないように、知事の椅子にしがみつくに違いないだろう。なぜならオリンピックというとてつもない利権が目の前にあるのだから、辞めるにやめられないだろ、それがマスゾエパーソナリティというものだからだ。
これらの問題は、遵法であるかどうかというより、モラル、行儀の問題であるから、結局はパーソナリティの問題に行きつくだろう。従って、例えいったん収まったところで、早晩また同じようなことに及ぶであろうし、もし舛添え氏が辞任、しまた選挙になっても、どうせ「マスゾエ気質」なる人物が知事になるであろうから、同じことの繰り返しになるだけだろうと危惧するのは小生だけだろうか?
彼の離婚した元妻で代議士の片山さつき氏が、テレビのインタビユーに応えて、「彼は、少しも変わっていないですね。それ以上は元妻としては言えませんが。」と言っていたが、おそらく小生が指摘した体質について同じような考えではなかったかと思う。
それを聞いた時に小生は、片山さつき氏は、舛添氏に比べれば存外真っ当な人物なのかもしれないと、不覚にも思ってしまった。
相対化とは実に恐ろしい思考様式であります。
*三菱自動車の燃費偽造問題は日産ゴーン社長のマッチポンプではないのか?
100年以上も時の権力に結びつき巨万の富を得てきた財閥と言う組織が国民の為を思う所業をするとは、元より考えにくいが、三菱自動車はトラックのタイヤが外れて死傷事故が連続して起きるまで、あえて不備を隠してリコールをしなかった事件に続いて、全自動車の燃費を全く虚偽の作文していた問題が発生した。
三菱自動車は、さすがに今回ばかりは三菱グループから見離されるのではないか、とみられていたが、間髪を入れずに日産が2000億以上出資して買収を決めた。
シャープのように、露骨な外資の買収の形をとらず、社員も株主も国民も良かったと感じたかもしれないが、肝心の燃費不正を告発したのが日産であるとなれば、話は出来過ぎではないだろうか?
三菱の軽自動車の技術力とアジア圏での販売力が欲しかった日産が、燃費不正をリークして三菱を窮地に追い込み、そこで白馬の騎士然として現れ、救いの手を差し伸べるかのように偽装し、有利な条件で買収した、と考えるのはウガチ過ぎた見方であろうか?
その後のゴーン氏の張り切りようを見るとあながち外れていないように思えるのである。
*蜷川幸雄の「枯れずに走り続ける」もついに止まった―そして死しても、その威厳に群がる人達
演出家の蜷川幸雄氏が80歳で亡くなった。僕はこの領域、業界に疎いので、彼の偉大さの本当の所は良くは分からないが、彼の逝去に際して実に多くの人が、彼から受けた薫陶を語っている。実際には大した関係でもなかろうようなジャニーズ系の人達も、われ先にと、恩人のごとく悼む言葉を述べているのは、なぜか自分のプロモーションのようにも聞こえてあざとくさえ思うほどである。
そんな中で、心に沁みる真情溢れる良い文章が日経新聞(2016.5.16)に載っていたので紹介する。
かつて自由劇場を率いていた劇作家で演出家の佐藤信の言葉である。
佐藤信が1971年に黒テントの旗揚げ公演を後楽園球場でした時、蜷川さんは自分の劇団仲間と一緒に観劇に訪れ、帰り際に「うん、俺たちのやりたいのとは違うけどな」と言って励ましたという。率直で心が通じる励ましであったと書いている。
蜷川さんは嘘の無い人であった。張ったりや衒い、ともすれば世渡りの手管の様なものばかりが見え隠れするような場所にいて、かたくなに、生真面目に、演劇を信じ貫き通した。後年授与された文化勲章をはじめ様々な「栄誉」をごく自然に身にまとい、同時に、すぐそのことを忘れさせてくれるような、根元的な飢えと怒りを手放さない生来の純粋さがそれを支えていた。
昨秋、酸素ボンベからのチューブを鼻に着けて車椅子で稽古場に登場する蜷川さんの様子をテレビで見た時、いつもの通り、照れを含んだ独特の微笑を浮かべており、「相変わらず元気だな」とやり過ごしてしまったが、ただ事でなかったのは、蜷川さんが酸素ボンベを手放さない自分の姿を、あえて世間に曝して見せたことだ。画面を通して発せられていたはずの、蜷川さんの生真面目さ、かたくなさに由来する覚悟のメッセージを読みとれず、浮薄で皮相な視線でやり過ごしてしまった自分の目の曇りが返す返すも情けない。
蜷川さんは晩年の5年間に40本近い、それぞれが傾向の異なる多彩な舞台を手がけた。彩の国さいたま芸術劇場でのシェークスピア全作品上演への挑戦、高齢者劇団さいたまゴールドシアタ―と若者劇団ネクストシアタ―の活動。三島由紀夫、福田義之、清水邦夫、井上ひさし、寺山修二、唐十郎から野田秀樹、ケラリーノサンドロヴィッチに至る幅広い劇作家の演出を手がけたが、特に60歳を過ぎてから多作になったという。
60代、とりわけ70代に入ってからの猛ダッシュを、自身は「枯れずに走り続ける」と表現していた。言葉をかえれば「あきらめずに求め続ける」ということだろうか。ここにも蜷川さんらしい純粋さの結晶がある。
演劇を「夢」や「未来」を通しては語りたくはない。そのような観念の世界に拡散することなく、「いま」「ここ」にある具体的な表現だけが、蜷川さんにとって演劇のすべてだった。蜷川さんは死後まで、飢えと怒りの感情を梃子に、執拗に演劇を問い続けた。だから休み無く舞台を作ることだけを、激しく自らに課して実行した。蜷川さんが最後まで心血を注いだ舞台そのものの痕跡は、既にどこにも存在していない。劇場とはそういう場所だ。
独り瞑目して、静かに旅立ちを見送る。
「拍手はなしな」、蜷川さんは言うだろう。
「枯れてたまるか」は彼の最後の生き様であった。
この一言だけで、僕は勇気がもらえる。