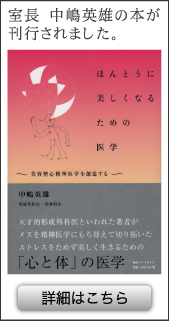地下鉄麹町駅から1分の紀尾井町の交叉点から徒歩一分くらいにある自称ネオビストロ、オー・プロバンソーに行った。
一度目はジョージ氏に薦められてクリニックのスタッフの誕生日会に行って、予想外に良かったので、5日後に裏を返し、その後、最近もう一度しっかり行ってみたので、このお店の様子は大体つかめた。
店構えはいかにもビストロ風で、中に入ると、インテリアもベンチシートになっており、パリのビストロを思いおこさせるが、(赤坂サカスのマキシムの色のように)、あちらでよくある真っ赤なビロードのクッションではなく、シックな茶系でまとめられている。それに、お店のお客の風景は猥雑なビストロ風ではなく落ち着いたプチレストランといったところだ。
名前からはプロバンス料理を想起させるが、料理はニンニク、オリーブ、トマトを使った、いわゆるプロバンス地方のメニュは一つも無く、ブイヤベースやスープ:ドゥ・ポアソンなど南仏の料理も数日前の予約が必要とのことであった。プロバンスに拘って見るなら、せいぜい料理に黒トリュフソースが多いかなと感じさせるくらいであったので、店名の由来には他の理由があるのだろうが、まだ聞いていない。
料理のサービスのスタイルはプリフィクスメニュが3種類だが、多彩なアラカルトメニュの前菜、魚料理、肉料理の中から自由に2品、3品、4品のチョイスで分けられており、使い勝手は非常に良い。お腹の具合で皿数も、内容も選択できることになる。
グラスワインの選択も良く、お店のレベルの高さをうかがわせる。
料理そのものはクラシックなフレンチで、味のメリハリのある上級なもので、コートドールの系統かと一瞬思ったが、メートルドテルの話では、シェフは溜池のビストロ、ボンファムの出身らしい。
直近で食べた料理をご紹介する。
前菜その1の「香ばしく焼き上げたタラバガニと根菜のサラダ柚子の香り」は、タラバガニに紅芯大根、青カブのスライスにコンソメのジュレがかかった一品で、柚子の香りも程良く、肉を主菜にするなら格好の前菜であった。
前菜のもう一皿は「セップダ茸のポワレとヴルーテ、フォアグラのコンフィ」を頼んだのだが、ヴルーテとは小麦粉のルーをフォンで伸ばしたポタージュのようなもので、それにセップ茸とフォアグラを蒸し焼きのようにしたものが真ん中に鎮座する皿であったが、キノコの歯ごたえとフォアグラの濃厚さがよく合い美味しかったが、ヴルーテという手法は個人的には珍しい料理であった。
連れは「鮑と若いポロネギのシフォナード、肝のソース」を注文した。これは私は食していないので、味は分からないが見た目には、鮑の肝のソースも鮮やかでいかにも旨そうであった。蒸しアワビに若いポロネギのみじん切りを散らした肝ソースをかけた、どこか和風に通じる、間違いのないお皿のようであった。
主菜は「京都中勢以さんの熟成但馬牛純米酒煮、グリ-ンペッパーソース」を頼んだ。
中勢以といえば、田園調布の赤身熟成肉とピンとくるが、聞くと中勢以は元々は京都伏見の肉屋が始まりのようである。しかもこの皿は赤身肉ではなくバラ肉のように油脂の多い部分が使われており、その熟成肉は初めての体験であったが、油のしっつこさが抜けて旨味だけは残したような芳醇な味わいでありながら、口中の油キレの良いとても洗練されたお皿でしたが、日本酒がどのように奏功しているのかは僕の舌では分からなかった。
とにかく、珍しい味わいの深い一品でした。
連れは「はたをふっくらと蒸しあげて、九条ネギのポテとロワイヤル」と、かなり込みいった料理を頼んだ。ポテとは豚と野菜の煮込み料理で、ロワイヤルとは卵とブイヨンで蒸し上げた卵豆腐のようなものを言うから、はたを卵とブイヨンで蒸し上げたものに九条ネギをフォンで煮込んだものを添えたもののようだ。
はたの旨味が良く出ていてとても美味しかったということでした。
デザートは洋ナシと柿のコンポ―ネントとフォンダンショコラで、フルーツは今が旬で、外しようがないが、洋ナシの方は、今の僕達の舌には、少し甘みが強すぎるようにも思えました。
デザートプレートは、前に来た時に、誕生日のサプライズでシェフからプレゼントされたお皿があまりにきれいな出来ばえだったので、ここでついでに紹介しておきたいと思います。誕生日が二人だったので、メッセージもフランス語と日本語の2種類が用意されました。
オー・プロバンソーの中野シェフは、かようにフランスの伝統的な技法を使ったいわばクラシックなフレンチを正統的に提供していますが、それは今の時代にはかえって新鮮で、逆にヌーベルキュジンヌのようにさえ見えます。
チーズも種類は多くはないが、良く熟成されたものが、ウオッシュもハードも、牛も山羊も揃っており、もう一杯の赤ワインと共に食後の愉悦が堪能できます。
オー・プロバンソーは、パリのビストロを上品にしたような、かと言って、グランメゾンのように構えるのでもなく、現在の日本には少なくなったフレンチらしい料理とサービスを伝える貴重なお店でした。
メートルドテルは勉強家で矜持を持って接し、ギャルソンもマドモアゼルもマナーは優れて良く、マダムは出しゃばることもなく、全体に目配りがきいていて安定感を醸し出し、お店の雰囲気はとても落ち着いていて、安心して心ゆくまで食事が楽しめる感じでした。
それに、コスパも大変良いです。
最近での久しぶりの☆三つ~です。
僕の美容整心クリニックからも歩いて数分の場所にあります。
いつでもお連れしますので、どうぞ皆さん、患者さんになって、(笑)お遊びにいらして下さい。